こんにちは。元小学校教員のたまごです。
6月後半からいよいよ水泳の授業が始まりますね。
初めてプール指導をする方は、上手くできるかドキドキしているのではないでしょうか?
わたしも初めは不安でいっぱいでしたが、水泳の授業には全学年共通の「手順」があると気づいてから、自信をもって指導ができるようになりました。
そんなわたしが、今回は「プール指導の手順」について、初心者の方に向けてわかりやすく解説します。
具体的には、1授業(45分)を
- STEP1:導入(10分)
- STEP1:展開(25分)
- STEP3:振り返り(10分)
の3ステップにわけて解説します。
ちなみに今回の内容は指導案ではありません。
あくまで「手順」なので、授業づくりのヒントぐらいの軽い気持ちで読んでくださいね!
プール指導にも役立つツールをこちらの記事で紹介しています。あわせてどうぞ。
教員の熱中症対策についてもまとめているので、ぜひご覧ください。
前提:指導内容が2学年ごとに分かれている
学習指導要領では、水泳系の領域として
- 低学年を「水遊び」
- 中学年を「浮く・泳ぐ運動」
- 高学年を「水泳」
で構成していて、指導内容が2学年ごとに分かれています。
そのため、本来なら2年間の指導計画をもとに水泳の授業を行うところですが、毎年担任が変わる小学校ではそれが難しい場合があります。
今年度の指導計画を立てる際には、前年度にどこまで学習しているかを必ず確認しましょう。
また、指導にあたる学年の教員全員で
などを共有してから、水泳の授業をスタートしましょう!
STEP1:導入(10分)
水泳の授業はタイムマネジメントが重要です。
とくに「導入」をどれだけスムーズに行えるかで、「展開」にかけられる時間が決まります。
導入の手順としては
- 準備運動・シャワー
- めあてやねらいを確認する
- 入水する
の3つです。これらをだいたい5~10分程度で行いましょう。
②の順番は、学校や指導者によって変わるので、学年で統一するとわかりやすいです。
③については、ハンドサインで入水方法を示すことが多いので、事前に確認しておきましょう。
STEP2:展開(25分)
入水後は、いよいよ授業のメイン「展開」です。
展開の手順は
- 水慣れをする
- 学年ごとの課題となる運動をする
の2つです。②に重点を置き、20~25分ほど時間をとりたいところです。
それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。
水慣れをする
「水慣れ」とは、子どもたちが水に慣れるための活動です。
水への恐怖心を取り除き、水中での動きを自然に行えるようにするための役割があります。
活動内容には、水の特性である「浮力」「抵抗」「水圧」を感じながら、呼吸したり脱力したりする運動を取り入れましょう。
具体的には
- 手のひらで水面を叩く(弱、強)
- 手のひらで水を押し出す(前、左右)
- 水をかけ合う
- 水に浸かる(鼻まで、頭まで)
- バブリング
- ボビング
- 水底タッチ(片手、両手、お尻)
- 水中じゃんけん
- 股くぐり
- ビート版に座る
- ビート版にしゃがむ
- ビート版に立つ
- ビート版を持って伏し浮き
- ビート版を抱いてラッコ浮き
- だるま浮き
- くらげ浮き
- 大の字浮き
- 伏し浮き
- 背浮き
などの運動があります。
いろいろな運動の中から、学年に応じたものを組み合わせて、水慣れを行いましょう。

5秒できるかな?10秒できるかな?と時間を計るのも面白いよ!
学年ごとの課題となる運動をする
水慣れが終わったら、休憩をはさんで「学年ごとの課題となる運動」に移ります。
こちらは学習指導要領解説に詳しく示されています。例示された運動は次の通りです。
低学年「水遊び」
水に慣れる遊び
○水につかってのまねっこ遊び、水かけっこ
○水につかっての電車ごっこやリレー遊び、鬼遊び
浮く・もぐる遊び
○壁につかまっての伏し浮き、補助具を使っての浮く遊び
○水中でのジャンケン、にらめっこ、石拾い、輪くぐり
○バブリングやボビング
中学年「浮く・泳ぐ運動」
浮く運動
○伏し浮き、背浮き、くらげ浮きなど
○け伸び
泳ぐ運動
○ばた足、かえる足
○連続したボビング
○補助具を使ったクロールや平泳ぎのストローク
○呼吸を伴わない面かぶりクロール、面かぶりの平泳ぎ
○呼吸をしながらの初歩的な泳ぎ
高学年「水泳」
クロール
○25 ~ 50 m程度を目安にしたクロール
平泳ぎ
○25 ~ 50 m程度を目安にした平泳ぎ
これらの習得を目指し、段階的な指導をします。
プールを横向きに何本か泳いでから縦向き(25m)に泳ぐなど、1つの授業内でもスモールステップで丁寧に進めていきましょう。
STEP3:振り返り(10分)
最後は、授業の締めくくりである「振り返り」です。
振り返りの手順は
- 振り返りをする
- 整理運動・シャワー
の2つです。5~10分にまとめ、チャイムが鳴る前に終わるようにします。
①では、自分ができるようになったことや友だちのよかったところなどを子どもに発表させたり、動きのポイントを共有したりしましょう。
また天候によっては、教室で振り返りをすることもあるので、ワークシートを用意しておきましょう。
まとめ:プール指導は見て学び、学習指導要領解説を読み込もう!
ここまで「プール指導の手順」を解説してきましたが、簡単にまとめると
- 準備運動・シャワー
- めあてやねらいを確認する
- 入水する
- 水慣れをする
- 学年ごとの課題となる運動をする
- 振り返りをする
- 整理運動・シャワー
という手順でした。
初心者の方は、授業づくりの材料のひとつとして、ぜひこの記事を参考にしてください。
初めのうちは、先輩教員が全体指導を担当してくれると思うので、その間にしっかり見て学びましょう。
そして、不安や迷いがあるときは、学習指導要領解説をしっかり読み込み、水泳指導の理解を深めましょう。

ここまで読んだあなたなら大丈夫!気負わず指導にあたろう!
参考文献:文部科学省(2017)『小学校学習指導要領(平成29年告示)解説 体育編』
文部科学省(2014)『水泳指導の手引き(三訂版)』
.png)

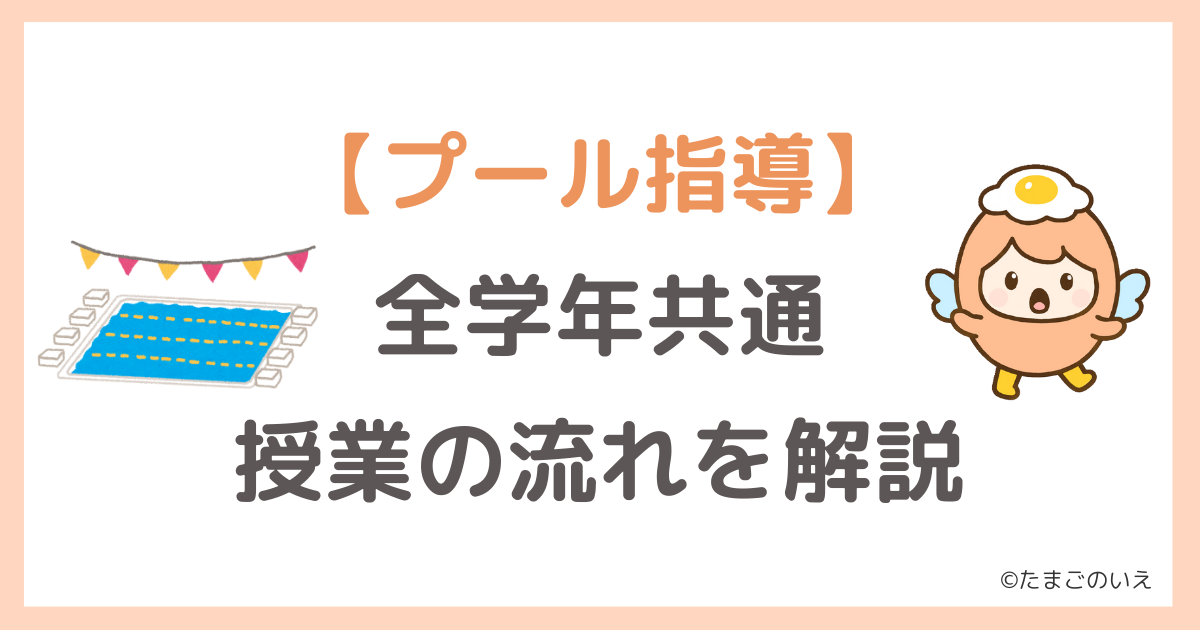
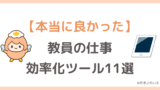
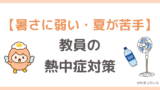
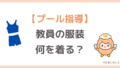
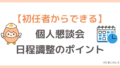
コメント