こんにちは。元小学校教員のたまごです。
新年度がスタートしましたね!
春の運動会がある学校は、そろそろ準備を始める頃でしょうか。
わたしは新任のときに、いきなり運動会のダンスを任されて、何から手を付けていいかわからず困り果てました。
そんなわたしでも、ベテラン教員から好評のオリジナルダンスをつくることができました。
そこで今回は「運動会のダンスのつくり方」について、新任教員の方に向けて丁寧に解説します。
具体的には
・ダンスのテーマを決める
・小物を選ぶ
・曲を選ぶ
・振付を考える
・隊形移動のしかたを考える
・入退場のしかたを考える
・衣装をつくる
をそれぞれわかりやすく解説していきます。

この記事を見たら、運動会のダンスづくりで、もう困らないよ!
ダンスのテーマを決める
テーマは振付や指導の指針となります。
きちんと決めて学年全体で共有しておきましょう。
決め方は
- 学年目標に合わせる
- 子どもたちが話し合って決める
- 担任が決める
の3つです。簡単に解説します。
学年目標に合わせる
学年目標とダンスのテーマをリンクさせる方法です。
例えば、学年目標が「明るく元気な〇年生」なら、そのまま使うことができます。
「元気」というワードに着目して、それをテーマにしてもOKです。

目指す姿に一貫性があってわかりやすいよ
子どもたちが話し合って決める
子どもたちが自分たちでテーマを決める方です。
・司会進行や書記を立て、クラス全体で話し合う
・グループごとに話し合って、それぞれ発表(プレゼン)する
などがあります。決め方を提示してあげると、子どもたちもスムーズに動けます。
この方法は、達成感や成功体験を得られやすく、教育活動の理想といえます。
しかし、学年や子どもの実態によって難しい場合もあるので、子どもたちに合った方法を選びましょう。
担任が決める
大人側であらかじめテーマを決めておく方法です。
担任が集まって話し合ったり、ダンスの指導担当が提案したりします。
特に低学年では有効な方法のひとつです。
小物を選ぶ
ダンスで使う小物は、予算や他学年との兼ね合い、取り扱いやすさなどを考える必要があります。
- 指定の小物があるとき
- 自由に小物を選べるとき
の2パターンを解説します。
指定の小物があるとき
学校によって1年生はポンポン、2年生はカラー軍手など、あらかじめ学年ごとに使う小物が決まっている場合があります。
指定の小物があるときは、学校に在庫があるのか、それとも新規購入が必要なのかを確認します。
もし在庫があるなら、数が足りるか、壊れていないかも必ず確認しましょう。

物品の発注から納品まで数週間かかるときがあるよ!早め早めに準備しよう!
自由に小物を選べるとき
基本的に大物(フラッグなど)は取り扱いが難しいです。
おすすめは、身に着けられて、振付にも活かすことができる物です。
例えば、カラー軍手なら踊っているときに落とす可能性が低いですし、ポンポンなら音を鳴らしたり文字をつくったりすることができます。
また色展開があると、色ごとに振付や移動ができるので、ダンスの幅が広がります。
学校にあるカタログで、どんな小物があるのかチェックしてみましょう!
曲を選ぶ
基本的には明るい曲調を選ぶといいでしょう。
有名な曲だと子どもたちの反応もよく、練習に取りかかりやすいです。
本番も間違いなく盛り上がります。
曲選びのポイントは以下の3つです。
- ミディアムテンポにする
- 歌詞の内容を確認する
- 好きな曲かどうか
それぞれ解説していきます。
ミディアムテンポにする
曲を選ぶときは、ミディアムテンポ(BPM90~110)がおすすめです。
これは子どもが無理なく足踏みできるぐらいのテンポだからです。
テンポがよくわからない場合は、使いたい曲にあわせて、自分で足踏みしてみましょう。
テンポが速いときは、音楽編集ソフトや音楽プレーヤーを使って調節することもできます。
歌詞の内容を確認する
基本的には次の2つのポイントをおさえるといいでしょう。
・不適切なワードが含まれていないか
・前向きな内容であるか
曲調、テンポ、歌詞の条件がそろえば、個人的には恋愛ソングでもいいと思っています。

歌詞によっては家族や友だちへの愛情に置き換えられるね
好きな曲かどうか
選曲で迷うときは、自分が「好きな曲かどうか」も判断材料の一つにしてみてください。
ダンスで使う曲は、振り覚えや指導のときに、繰り返し聴くことになります。
何度も聴きすぎて「もう聴きたくない」という気持ちになってしまうと、指導の時間が憂鬱になります。
楽しんで指導を続けるために、自分が好きな曲を選びましょう!
振付を考える
振付はポイントさえおさえれば、初心者でも意外と簡単につくることができます。
つくり方は
- 振付動画を参考にする
- オリジナル振付を考える
の2つです。それぞれ詳しく解説していきます。
振付動画を参考にする
YouTubeなどの動画共有サービスには、運動会のダンスの振付動画がたくさんアップされています。
ダンススクールの先生など、プロの方が選曲から振付までしてくれているので、ぜひ活用しましょう。
動画の振付をそのまま使ってもOKですが、難易度を調節するためにアレンジを加えても良いですね。
学校等の教育機関において、小説、絵、音楽などの作品を利用する場合、
その公共性から、一定の範囲で自由に使うことができます。
詳しくは、文化庁の『学校における教育活動と著作権』をご覧ください。
オリジナル振付を考える
曲の1番と2番は同じ振付にできます。
そのため振付は1番のAメロ、Bメロ、サビを考えるだけです。
ダンスでは、8カウント(音楽の2小節分)をひとまとまりとして、1×8(ワンエイト)と呼びます。
振付も1×8ずつ考えていくと良いでしょう。
基本的にダンスは「1・2・3・4・5・6・7・8」のカウントに合わせて踊ります。
例えば
「1」で右手を挙げ
「2」で左手を挙げ
「3・4」で腕を組み
「5・6・7・8」で両腕を大きく外に回す
これが1×8(ワンエイト)の振付です。
振付の手順としては
① 曲を聴いて振付のイメージを膨らませる
② カウントを取りながら曲を聴き、Aメロ、Bメロ、サビでそれぞれ1×8がいくつ分あるのかを把握する
③ Aメロ、Bメロ、サビの中でつくりやすそうなブロックから、1×8の振りを必要数分つくる
④ ③で考えたAメロ、Bメロ、サビのそれぞれの振りを繋げる
です。
しゃがむ、ジャンプ、ターン、ステップなど、上下・左右・前後に動く振りを取り入れると、ダンスに立体感がでます。
どうしても振りが思いつかないときは、いろいろなダンス動画を見て、取り入れたい振りを探してみましょう。

初心者でも簡単にオリジナル振付ができそう!
隊形移動のしかたを考える
隊形移動のポイントは以下の3つです。
- 隊形移動の目的
- 隊形の種類
- 移動のタイミング
それぞれ詳しく解説していきます。
隊形移動の計画を立てるときは、iPadがあると便利です。こちらの記事で紹介しています。
隊形移動の目的
隊形移動の目的によって、隊形の種類や移動の回数が変わってきます。
まずは何のために隊形移動をするのか考えてみましょう。
わかりやすように例をあげると
・低学年では、簡単な振付だから見ばえを意識するため、隊形移動を多くする
・高学年では、一人ひとりを際立たせるため、あえて隊形移動をしない
などの場合があります。目的によって全くちがいますよね。
個人的には、学年に関係なく、隊形移動を1、2回するのが適当ではないかと思っています。
その理由は
どの子も必ず1回は、保護者からよく見える位置にするため
です。
子どもたちは、保護者にこそ1番見てもらいたいはずです。
保護者もまた、子どもの活躍をより近くで見たいと思われるでしょう。
隊形移動を考える際は、ぜひ目的から逆算して考えてみてください。
隊形移動は、なるべく移動距離を短く設定すると良いでしょう。
保護者の多くは撮影しながら観覧されますが、子どもが左右に大移動すると、フレームアウトしやすくカメラで追うのが大変です。
そのため、カメラのズーム調節だけで済むような、前後の入れ替えがおすすめです。
隊形の種類
隊形の種類は、円、V字、十字、横1列、トラック上などが定番です。
クラスごとに円をつくったり、全員で大きな十字をつくったりできます。
上記のアレンジとして、円ごとにワンエイトずつ踊ったり、十字を風車のように回転したりすることもできます。
またトラック上に並ぶ隊形は、観覧席に1番近づけるので、取り入れる人が多いです。

最後の隊形からどうやって退場するかも考えておこう!
移動のタイミング
移動するタイミングは、曲の間奏やCメロにすると、子どもたちにわかりやすいです。
曲のながれ「1番→2番→大サビ」に合わせて、「体操隊形→円→トラック上」のように移動します。
実際に隊形移動をしてみると、どうしても時間内に完了しないことがあります。
計画の段階から、移動距離を短くして、時間も長めに設定しておくと良いでしょう。
入退場のしかたを考える
入退場も団体演技の一部です。
ダンスの振付や隊形移動と同じように、詳細までしっかり考えておきましょう。
入退場は、演出と選曲の両方からアプローチすることができます。
・演出にあわせて曲を選ぶ
・曲にあわせて演出を考える
の2パターンです。
例えば
・カッコよく行進しながら入場させたい ↔ 歩きやすいテンポでリズム感がいい曲
・飛び出すようにスキップしながら入場させたい ↔ アップテンポで元気な感じの曲
・保護者席に一礼してから退場させたい ↔ 感謝の気持ちを伝える歌詞の曲
などです。どちらからでもアプローチできますね。
演出と選曲のどちらを先行させるかは、学年やダンスの雰囲気に合わせて決めるといいでしょう。
衣装をつくる
基本的な考え方は小物選びと同じですが、こちらでは
他教科と連携する方法を紹介します。
衣装制作は、図画工作科など制作内容に合った時間を使って、年間指導計画に沿いながら行います。
衣装はスカーフやマント、T シャツ、ハッピなど、いろいろな種類があります。
これらにアレンジを加え、世界に1つだけのオリジナルの衣装を作ることができます。
例えば
・カラーポリ袋を切り開き、リボンを通して、マントをつくる
・無地Tシャツに、アクリル絵の具で好きな文字やことばをかく
などが考えられます。
衣装制作を通して、子どもたちはますます運動会が楽しみになるでしょう。
時間や予算に余裕があれば、ぜひ実施してみてください。
まとめ:運動会のダンスづくりは、結局実践あるのみ!
ここまで長々と解説してきましたが、やってみないことにはわからないので、結局実践あるのみです!
わたしも初めは試行錯誤しながらでしたが、頑張ってオリジナル振付に挑戦したおかげで、経験値がかなり上がった実感がありました。
あえて難しい方を選んでやってみると、経験値がぐんと溜まって、次の機会には楽にできるようになりますよ。
でも、経験もないままに、いきなりダンスをつくることになったら、正直不安ですよね。
そんな新任教員の方が、少しでも自信をもって運動会に臨めるように、この記事を書きました。
わからないことは、どんどん周りの人に聞いて、今年度の運動会のダンスをつくりましょう!

運動会ファイトーーーー!!!
.png)

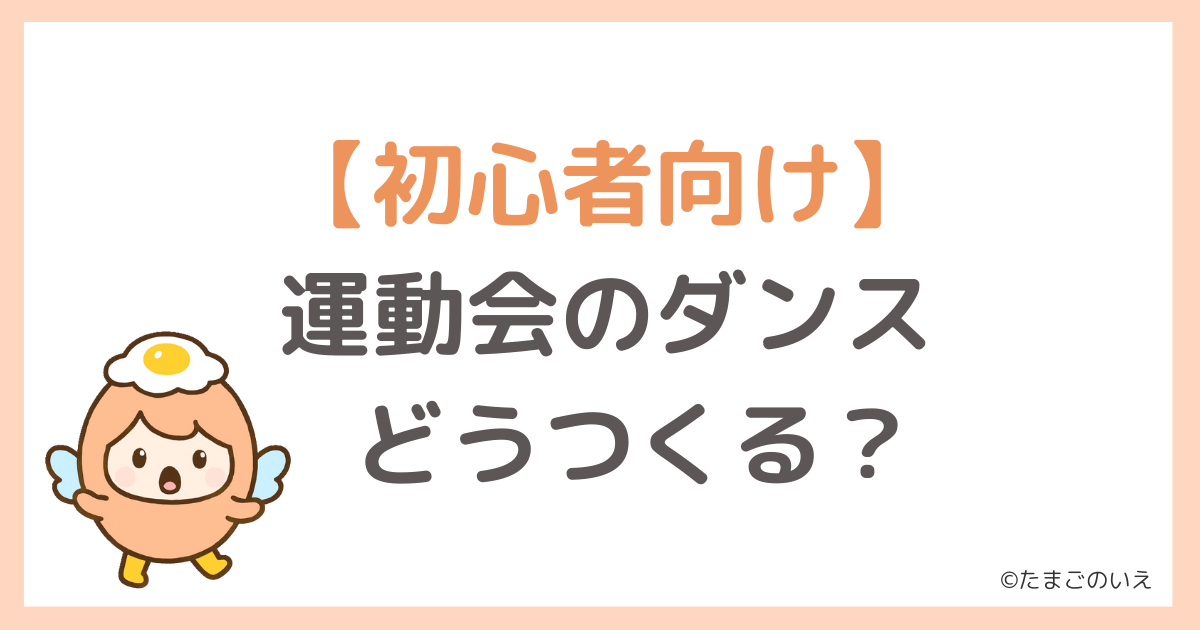
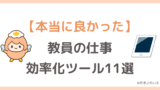

コメント