こんにちは。元小学校教員のたまごです。
個人懇談会は7月ですが、その日程調整が6月から始まりますね。
これが意外と大変で、教員間で事前に相談しなければならないことが山ほどあります。
わたしは新任の頃、他クラスの日程表をチェックできてなくて、膝から崩れ落ちる出来事がありました。
そんなわたしが、今回は「個人懇談会の日程調整」のポイントについて、新任教員の方に向けてわかりやすく解説します。
具体的には、個人懇談会までの次の4つの流れ
- 個人懇談会のお知らせを配布
- 希望日時の用紙を回収
- 日程調整
- 日時決定のお知らせを配布
に沿って、それぞれの段階でおさえておきたいポイントを解説します。
オンラインで日程調整ができる学校の場合は、①、②、④を飛ばしてもらって大丈夫です。
個人懇談会のお知らせを配布
まずは「手紙の配布」です。
ここで大事なポイントが2つあります。
- 手紙が保護者に渡るようにする
- 用紙の提出期限を守ってもらう
これらを意識して行動することで、用紙の回収スピードや回収率が格段に上がります。
例えば、わたしは
- 手紙を必ず保護者に渡すよう子どもたちに言う
- 用紙の締切日を子どもたちにも伝える
- 連絡帳に「個人懇談の手紙(〇日締切)」と具体的に書く
を実行していました。
学校のサポートが必要な家庭には、直接電話をして知らせることもあります。
希望日時の用紙を回収
次は「用紙の回収」です。締切を設けているので、基本的には期限まで待ちます。
しかし、ただ待っているだけでは回収率は上がりません。
手紙を配布した翌日から締切まで、毎日全員の提出状況をチェックして名簿で管理します。
そして未提出者には、次の3つのポイントを確認します。
- 用紙の提出し忘れがないか
用紙を持ってきているのに、出し忘れているパターンです。
出し忘れがないかクラス全体に一声かけるといいでしょう。
- 手紙を保護者に渡したか
手紙を保護者に渡し忘れていたり、手紙をなくしたりしているパターンです。この場合は個別に対応します。
- 保護者が予定の調整をしているか
手紙を保護者に渡したが、まだ提出していないパターンです。
予定の調整に時間がかかりそうな場合は、期限まで待ちます。そうでない場合は個別対応です。
さらに未提出が続くときは
- 締切前日:連絡帳に「個人懇談の手紙(明日まで)」と書く
- 締切当日:直接電話をして希望日程を聞く
など、締切のタイミングで全員分の希望日時を集められるように手を打っておきましょう。
日程調整
さて、必死に用紙を回収した後は、いよいよ「日程調整」です。
ここで大事なポイントは3つあります。
- 兄弟姉妹関係に配慮する
- 特別支援に配慮する
- 勤務時間外は管理職に相談する
それぞれ詳しく解説していきます。
ちなみに日程表ですが、学校で共通のフォーマットがないときは、自分で用意します。Wordで簡単な見本を作成してみたので、ご活用ください。
兄弟姉妹関係に配慮する
同じ学校に兄弟姉妹がいる場合、保護者が連続して個人懇談会に臨めるように、教員同士でスケジュールを調整します。
学校によりますが、基本は先に日程表が完成したクラスに合わせて、後から日程を組む人が調整します。
このような場合、まず兄弟姉妹がいるクラスの日程表を確認して、その前後どちらかに連続するように調整します。
そして、自分のクラスの日程表が完成したら、兄弟姉妹クラスの担任に知らせます。
同じように、自分のところにも続々と兄弟姉妹クラスの日程表が届くはずなので、自分より後から調整された日程表も必ず確認しましょう。
この確認、めっちゃ重要です!
たまに兄弟姉妹が連続になっていなかったり、逆にダブルブッキングされていたりすることがあります。発見次第、該当クラスの担任に確認をとりましょう。
最終的に、全ての兄弟姉妹クラスの日程表を確認して問題なければOKです。
特別支援に配慮する
特別支援学級に在籍している子の個人懇談会は、クラス担任と特別支援担当が同席して行う場合や、それぞれ分かれて行う場合があります。
まずは、どういう形で個人懇談会を行うのか、特別支援の教員に確認します。
もし同席して行うなら、その分話す内容も増えるので、長めに時間をとりましょう。
また在籍がなくても、特別支援関係の話をする予定があるときは、同じく長めに時間をとっておくといいでしょう。
勤務時間外は管理職に相談する
保護者にもいろいろな事情があるので、こちらの勤務時間外の時間を希望されることがあります。
しかし、公立学校の教員は原則として、給特法の「超勤4項目」以外に時間外勤務を命じられません。
個人懇談会を含め、この4項目以外の時間外勤務は、教員の自発的な活動とみなされます。いわゆるサービス残業です。
緊急対応や事務作業などで残業するならわかりますが、個人懇談会はれっきとした学校の年間行事です。
それを教員の自発的な活動(サービス残業)として、あらかじめ予定に組み込むのは、何だかおかしな話ですよね。
まずは、電話懇談や期間外の日程で調整するなど、勤務時間内に収めるための代案が実施できるか考えましょう。
もし、どうしても勤務時間外になってしまうようなら、必ず管理職に相談して許可を得ましょう。
日時決定のお知らせを配布
さいごは再び「手紙の配布」です。
最初の手紙を配布したときと同じように、手紙が保護者に渡るように意識して、子どもたちに声かけをしたり連絡帳に書いたりしましょう。
このとき、学校のサポートが必要な家庭には電話で知らせておくと安心です。
まとめ:日程調整ではリスク管理が大事!
以上、「個人懇談会の日程調整」のポイントを解説しました。
声を大にして言いたいことは、とにかくリスク管理がとても大事です。
気を付けることが多くて手間かもしれませんが、トラブルが起きるよりは断然マシなので、考えられるトラブルは未然に防ぎましょう!
新任教員の方や初めて学級担任をもつ方は、ぜひこの記事を参考にして、日程調整を進めてください。

確認、確認、確認……その確認があなたを助ける!
.png)

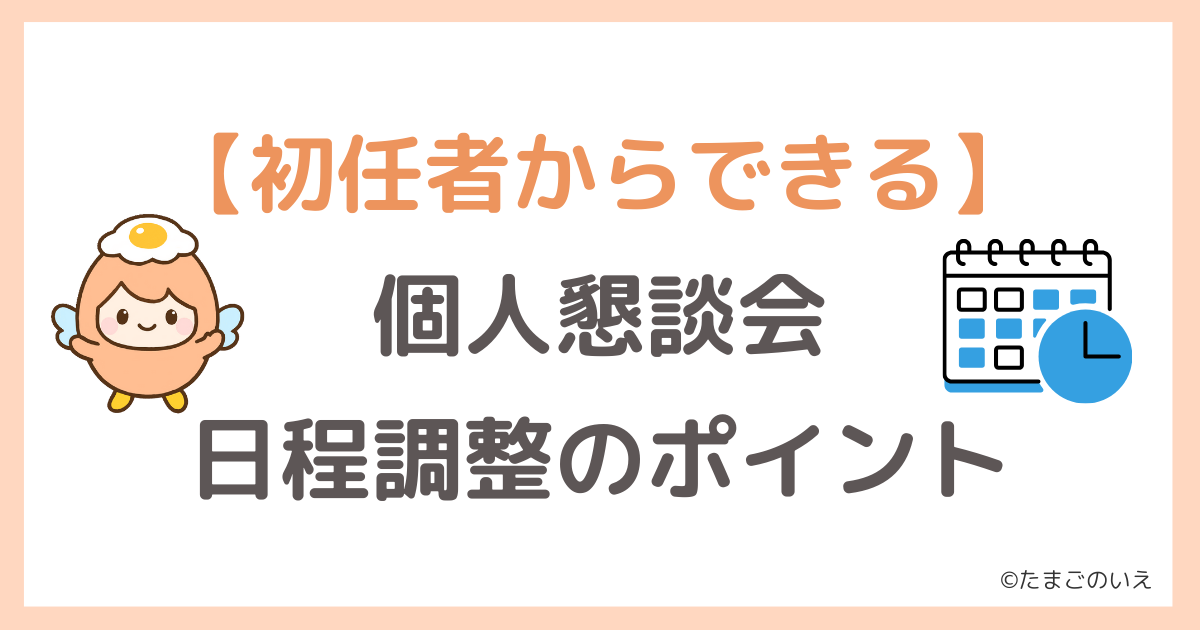
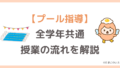
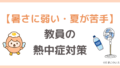
コメント